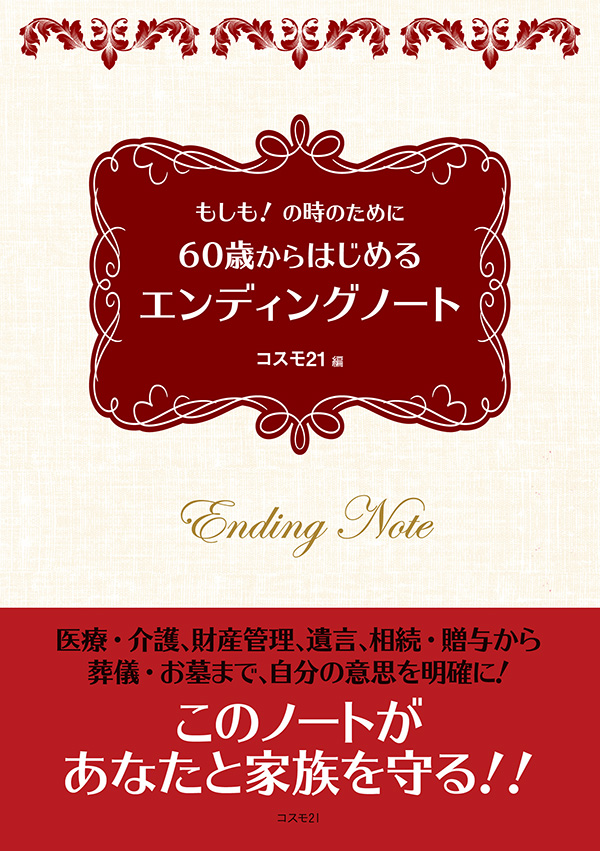60歳からはじめるエンディングノート
60サイカラハジメルエンディングノート
もしも!の時のために
コスモ21編
このノートがあなたと家族を守る!!
①あなたが生きてきた証をまとめ、②60歳を区切りとして第二の人生の新スタートを切る覚悟を書きしたため、③万一の時に備えて必要な情報や家族へのメッセージを正確に伝える——。本書は、書き込み式のノートのページと、必要知識を解説したページを組み合わせて、1冊にまとめてあります。あなたと愛する家族のために、この『エンディングノート』を活用してください
立ち読み
60歳からはじめる もしもの時の人生設計────はじめに
◇◇◇ 将来、家族を困らせないために
高齢化社会に突入していますが、60歳代の人は、まだまだ元気に毎日を過ごされていることと思います。仕事をバリバリこなしていたり、退職して趣味や地域のサークル活動で第二の人生を楽しんでいるなど、生活パターンはそれぞれでしょう。
しかし一方で、生活習慣病を患って病院通いを余儀なくされ、長年の運動不足による身体の老化、とくに足腰が弱り、階段の上り下りが苦痛という方もおられるのが現実です。
さて、この『60歳からはじめるエンディングノート』は、次のようなことにとても役立ちます。
①過去の清算──これまでの人生を振り返りつつ整理・大掃除する。
②未来の設計──還暦を機に、新しい人生をスタートさせるべく道標を確立する。
考え方や物事の判断力、足腰のしっかりしている60歳の今だからこそ、これからの数十年の生き方を自分自身に問いかけ、毎日を楽しく悔いなく過ごすための「終活ノート」とする。
③家族との意思疎通──①、②を明確に記しておくことで、あなたの考え、気持ちが家族に正確に伝わり、もしもの時に家族が判断に困らない「確認ノート」とする。
第二の人生がスタートする60歳だからこそ、自分の老後設計を新しくプランニングしましょう。そして、そのプランとともに、医療・介護のこと、財産管理のこと、遺言書のこと、相続・贈与のこと、葬儀・お墓のこと、自分の履歴・人生について等々、あなたの意思をこのエンディングノートで家族に伝えたり、現金や財産、銀行通帳・カード、実印、遺言書などがどこに保管されているのか、家族にわかるようにしておきましょう。
祖父、親、子ども、孫と続く世代が一つ屋根の下で暮らすという大家族のかたちが消えて久しくなりました。
親子でも同居する世帯は少なくなっています。親と子が年に数回しか会わないということも珍しくありません。
そんななかで、もしもあなたが不慮の事故に遭遇したり、突然の病魔に襲われて緊急入院せざるを得ない事態が発生して、意識が混濁したりなくなったりした時は、すべての対応を家族が背負うことになります。
医療費の支払い、保険の支払い申請、高額医療費の申請作業、毎月の各種支払い……などがすぐに発生します。何がどこにあるかわからない状態では、家族は困惑するばかりです。
そんな時に、「大事なものはどこに保管されているか」「もしもの時に、家族の誰の判断に任せるのか」などが明確に示されていれば、「あれはどうなっている?」「これはどうすればいい?」といったことがなくなり、スムーズに事が運べます。
本書は、そのための記録帳なのです。
ここで一つ、大切なことがあります。『エンディングノート』を作ったからといって、自分だけの『秘密のノート』にしてはいけないということです。
正月休み、ゴールデンウィーク、夏休み、墓参り、誕生日祝い……など、家族がそろって集まる機会を活用して、この『エンディングノート』を公開し、家族と話し合う「場」を持つことが極めて重要です。あなたの意思を伝えるには、繰り返し確認することが大切です。
もしもの時になって初めて『エンディングノート』の存在を家族が知っても、あなたの一方的な意思表示になってしまいます。
◇◇◇ 老前整理のすすめ
自宅には、不要と思われる生活用品やさまざまな荷物があふれかえっていることも多いでしょう。
重い物や、戸棚や本箱の上といった高い所の物は、高齢になり、手や足腰の動きが弱まってくると、自分では片付けられません。
そこで、60歳を人生の一区切りとして、家の中のすべての物を見直し、元気な60歳だからこそ「老前整理」することを、本書は切に願うものです。たとえば──。
●衣──何年も何十年も袖を通していない衣類が、箪笥や押し入れの段ボールの中に日の目を見ずにぎゅうぎゅうに眠っていませんか? 思い切って処分しましょう。
●食──何年も何十年も食卓に出ていない食器や皿、カップ、グラスが、食器棚やキッチンの収納棚に眠っていませんか?
また、結婚式でいただいた引き出物がそのまま箱の中に……これらも、思い出の品や愛着のある食器、高級品を除いて、思い切って処分しましょう。
●住──整理箱や収納棚が不要物であふれかえっていませんか? 押し入れの中にも、何十年と触れたことのない荷物があるかもしれません。書棚にも、再び読まれることはない本の数々。これらも整理しましょう。
◇◇◇ バリアフリーな住まいに
この本をお読みになる方は、老眼は少し入っているけれど、足腰は丈夫で、日常生活には不自由を感じていない、という方が大半でしょう。
でも、だからこそ、元気で過ごしている60歳という節目に、家の構造を見直してみてはいかがでしょうか。玄関から台所、居間、寝室、風呂、トイレ、階段……と、今は何不自由なく暮らしている我が家ですが、ちょっと待ってください。
明日か、1年後か、5年後か、いつとは言えませんが、家のちょっとした構造に大きな危険が潜んでいることを認識しましょう。
●つまずいて転倒する恐れのある個所を見直しましょう
部屋やトイレの敷居のわずか数ミリの段差につまずいて転倒し、骨折したり、頭を打って大ケガ……などという話を、あなたの身近で聞いたことはありませんか?
東京消防庁のデータで、2008年から12年までの5年間を見ると、高齢者の事故は年々増加しています。
2008年には、高齢者の救急搬送は45,408人でしたが、2012年には約14,000人増加し、59,401人が救急搬送されています。
事故原因は、「ころぶ」事故がなんと全体の約8割を占め、次に「落ちる」事故が1割強と、普段の生活の中で事故が多く発生しているのです。
ちょっとした段差や階段で転倒や転落が多く発生し、高齢者が医療機関に救急搬送され、長期入院を余儀なくされています。
そんなことにならないよう、元気な今のうちに、我が家を安心して暮らせるバリアフリーな空間にリフォームしましょう。
将来、身体が不自由な状態になった時、寝室が、居間が、台所が、バス・トイレが、階段が、バリアフリーにリフォームされていれば、あなたも家族も慌てることなく過ごすことができるのです。
◇◇◇ 本書の目的・使い方
『エンディングノート』は、①あなたが生きてきた証をまとめ、②60歳を区切りとして第二の人生の新スタートを切る覚悟を書きしたため、③万一の時に備えて必要な情報や家族へのメッセージを正確に伝える、そのためのノートです。
本書は、書き込み式のノートのページと、必要知識を解説したページを組み合わせて、1冊にまとめてあります。
あなたと愛する家族のために、この『エンディングノート』を活用してください(記入した日付も余白に書いておきましょう)。
まずは、あなた自身のために本書をお使いください。これからをどう生きるかという確認作業のために、本書を活用してください。
そうすることで、万一の時の対処法が具体的に見えてきます。不安がやわらぎ、これからの人生の道標となってくれます。
また、本書は家族、とくに配偶者や親子間で、財産管理・相続の問題について話し合いの場を持ち、お互いに確認・納得するためのコミュニケーションツールにもなってくれます。
親子だから、配偶者だから、自分のことはわかってくれるだろうと、これらのことは往々にして軽視しがちですが、それが後々大きなトラブルを生みます。
そうならないためにも、本書を存分に活用してください。
目 次
もくじ・・・60歳からはじめるエンディングノート
はじめに──60歳からはじめる もしもの時の人生設計
将来、家族を困らせないために/老前整理のすすめ/バリアフリーな住まいに/本書の目的・使い方
第1章 医療・介護 ――もしも! の時に――
●私の身体の健康データ
●私の病歴、健康診断データ
●私が重篤な病状になった時の告知と過ごし方
●重篤な病状で回復する見込みがなくなった時
●要介護となった時の私の希望
●介護保険サービスについて
●介護費用について
●各種老人ホームについて
●認知症になった時
●脳死状態になった時の延命措置と尊厳死
●臓器提供と献体について
●尊厳死の宣言について
●臓器提供意思カードについて
第2章 財産管理 ――もしも! の時に――
●私が財産管理できなくなった時
●私の預貯金について
●私が加入している保険について
●私の不動産について
●私が保有する株式について
●私が保有する有価証券について
●私の動産について
●私のクレジットカードについて
●私の権利関係について
●私の貸付金について
●私の借入金・負債について
●私の金庫・貸金庫について
●私がこれまでに加入した年金について
●形見分けについて
第3章 遺言書 ――もしも! の時に――
●遺言と遺言書について
●遺言書の形式は3種類
●遺言を書く──自筆証書遺言
●遺言を書く──公正証書遺言
●遺言書、ここがポイント
●トラブルを避けるための遺言書の書き方
ケース1 配偶者と子どもたちがいる場合
ケース2 子どものいない夫婦の場合
ケース3 幼い子どもがいる場合
ケース4 独身者の場合
第4章 相続・贈与 ――もしも! の時に――
●遺言書の有無について
●遺産分割にあたって、私の希望
●相続手続きについて
●名義変更について
●法定相続人について
●法定相続の遺産分割について
●相続税について
●贈与について
第5章 葬儀・お墓 ――私の覚え書――
●葬儀の希望と死亡通知
●葬儀予算と費用の準備
●宗教・宗派、戒名について
●依頼する葬儀会社、葬儀の場所
●お通夜と告別式について
●喪主、葬儀委員長、弔辞について
●遺影、祭壇・飾り付け、音楽について
●死装束とお棺の中に入れてほしいもの
●香典と生花について
●葬儀参列者へのメッセージ、献花について
●葬儀参列者への会葬礼状・礼品
●香典返しと寄付
●もしもの場合に連絡してほしい人
●お世話になっている親しい人
●お墓と納骨について
●先祖代々のお墓について
●供養・法要の予算、費用
●仏壇・普段の供養、お墓参りについて
●永代供養について
●パソコンデータ、日記、手紙、写真など処理
●インターネットのデータ処理
●私が愛するペットの処遇
●所属している団体、サークルなど
第6章 私の履歴&人生ノート
●私の誕生
●私の学歴
●私の職歴
●私が所有する資格・免許、私の賞罰
●私の性格
●私の趣味・嗜好
●私たち夫婦の出会い
●結婚式・新婚旅行の思い出
●私たち夫婦のハイライト
●私たちの子どもの思い出
●両親の思い出
●配偶者の両親の思い出
●兄弟・姉妹の思い出
●祖父母の思い出
●甥・姪たちの思い出
●孫・ひ孫たちの思い出
●今、家族について気がかりなこと
●今、自分自身について気がかりなこと
●敬愛する大切な人へのメッセージ
●直近の家系図について
●私の兄弟・姉妹の子どもたち
●配偶者の兄弟・姉妹の子どもたち
[付録] 私が生きた時代と私の足跡──1945(昭和20)年〜