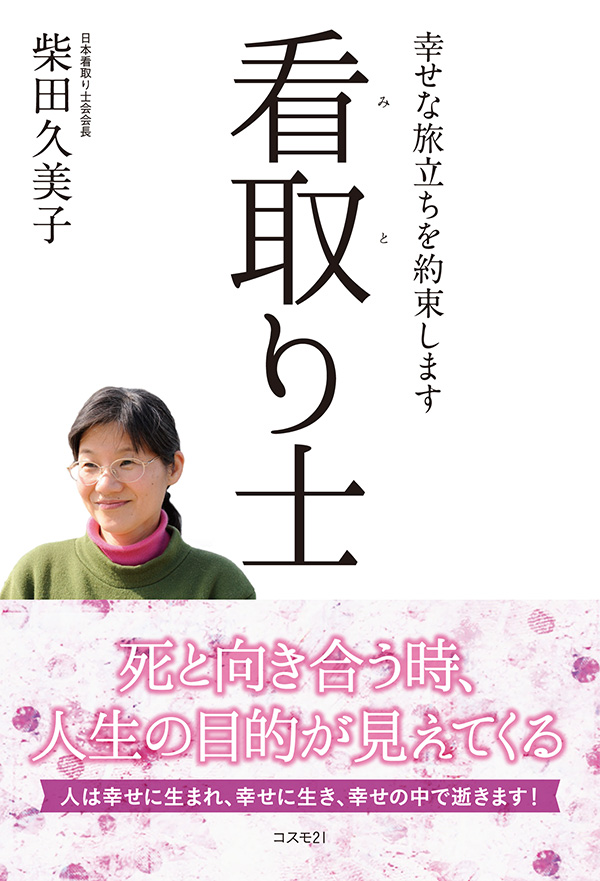幸せな旅立ちを約束します 看取り士
シアワセナタビダチヲヤクソクシマス ミトリシ
柴田久美子著
死と向き合う時、人生の目的が見えてくる
旅立つ人の本当の気持ちを伝えたい。しあわせに死ぬためにはどうすればいいのか、著者は、本書を通して一人でも多くの人が「看取り士」という存在を知り、生きる意味や死の意味に気づいてほしいと願う。
立ち読み
まえがき
「看取り士」とは文字通り、旅立つ人を看取る人のことです。私は、10年前から看取りの仕事をしていますが、2年前に「看取り士」と名乗り始めました。
この「看取り士」という職業は、おそらく日本で初めてだと思いますし、高齢社会を迎え孤独な死を余儀なくされている方々があまりにも多いこの国に、なくてはならないものだと思っています。
では、看取り士は何をするのかと言いますと、住み慣れた自宅やご本人の希望する場所で自然な最期を迎えたい人に、24時間寄り添い、旅立ちを支援します。旅立つ方が悔いなく、しあわせに人生を全うするため、ターミナル(回復の見込みがない段階)から納棺の前までのすべてを相談に乗り、ご家族の方とともに見送ります。つまり、ご本人が思い通りに旅立っていけるように調整していくのが看取り士の仕事です。
具体的には、お墓のこと、葬儀のこと、医師との連携などをし、どこでどのように最期を迎えるかをプロデュースします。
そして、いよいよ看取りの場面になると、そこには四つのポイントがあります。
まず一つに、旅立つ人と肌の触れあいをすること、二つ目に、傾聴、反復、沈黙を繰り返すこと、三つ目に、大丈夫と声をかけること、四つ目に、旅立つ人と呼吸を共有することです。詳しくは第2章に譲りますが、しあわせに旅立つためのプロデューサーといったところでしょうか。
「看取り士」は、看取りの現場で、旅立つ人そのものになって、旅立つ人の思いや愛やパワーを受け止め、残った人に受け渡すのです。看取りの場面では、奇跡的なことが起こります。しかし、それは奇跡ではなく、すべてが予定されたことのように感じます。
私の「看取り士」の原点には父の死があります。
小学6年の浅い春の日、最愛の父が旅立ちました。
胃ガンで余命3ヶ月。自宅の父の部屋の障子は光に包まれていました。
人々に囲まれて父は、一人ひとりに「ありがとう」を伝えます。最後に末娘の私の手を握り締め「ありがとう。くんちゃん」と微笑みました。そしてその手は冷たくなり、硬くなりました。父の目はもう二度と開くことはありませんでした。人の死が感動であり、とても尊いものと父は自らの死をもって教えてくれました。
私の尊敬するマザーテレサはこう言われました。「人生のたとえ99%は不幸だとしても、最期の1%がしあわせならば、その人の人生はしあわせなものに変わる」と。
この言葉に出合い、すべての人々が愛されていると感じて旅立てる社会作りを志として15年前より活動を始めました。
当時、都会の高級老人ホームに職を求めましたが、そこは医療依存度が高く自分で自分の最期を決める自由はありませんでした。
白い壁を見つめながら死に逝くたくさんの人々との別れはつらく耐え難いものでした。しあわせな死は病院のないところにあるように感じ、病院のない離島に行こうと決心しました。
そして1998年、人口600人の病院のない島根県隠岐の知夫里島に渡ります。そこで、ホームヘルパーの仕事を4年間した後、医療のないなかで看取られながら死にたいという方々をお預かりする看取りの家「なごみの里」を立ち上げました。
産まれ出た時、母親に抱きしめられたように、逝く人々を抱きしめて看取りながらたくさんの大事なことを教えていただきました。
いまは鳥取県米子市に拠点を置いて「看取り士」としてターミナルから納棺前までのお世話をさせていただいています。また看取りのボランティアであるエンゼルの活動(145ページ参照)にも力を入れています。
あの瀬戸内寂聴さんはこう言われました。「人間は旅立つ時、縁ある人に50メートルプール50倍ものエネルギーを渡していくものだ」と。
長い人生を終え、その生きる力を今度は次の世代の者に手渡す。その場面は決して悲しい別れではなく、愛と喜びに満ちた瞬間です。それが死なのだと思います。
今年始め、一通の年賀状が届きました。
その年賀状には「私はガンのステージは5です。2軒あった持ち家も1軒は処分しました。そして、医療は受けないと覚悟を決めました。
さて困ったことが一つあります。私は死を覚悟したものの、亡くなった後、一人で棺桶まで歩けないことに気がつきました。御相談に乗ってください」こんな文面でした。
私はすぐに電話を入れ、その女性に会いました。そして、何かあれば名古屋の看取り士がすぐに駆けつけることを約束して、日々の暮らしを支えていくことになりました。
彼女は、来てくれたことを、とても感謝をしながら手を取りこう言いました。
「柴田さんがいて良かった。これで私は何も心配することがなくなった。安心して生きていける。何かあったら連絡します」
在宅死を覚悟した彼女の潔さ。そして、私たちを頼りにしてくれるその女性の凛とした生き方に、私自身、とても励まされました。
抱きしめて送り、私のこの腕の中で最期の呼吸を終えたその人々が私にその身体を使って教えてくれたこと、その尊い経験を私は私一人のものとはせず、一人でも多くの方に伝えたい。
この本には『看取り士』というタイトルがついていますが、言い換えれば、旅立つ人の本当の気持ちを伝える本であるとも言えるでしょう。
しあわせに死ぬためにはどうすればいいのか、旅立った人たちと心が一つになった多くの経験をした「看取り士」という特権で書いたものです。
最期のしあわせな時間を手にするために、この本がお役に立つことができれば幸いです。
今後、日本では団塊世代の本格的な看取りが始まります。現在では110万人程度の年間死亡者が、この団塊世代の“参加”で160万人から180万人になると言われています。
まさにこれからは、“多死社会”を迎えることになり、看取りを担う私たち「看取り士」の責任はますます重大になってくるものと思われます。
ですから、本書を通して一人でも多くの人が「看取り士」という存在を知り、生きる意味や死の意味に気づいていただければ幸いです。
目 次
もくじ・・・幸せな旅立ちを約束します 看取り士
まえがき
第1章 看取りの瞬間
●看取りの瞬間に親子になれた、千代さん
●心と心が重なる旅立ちの時……マサさんとの12年の歳月
●ただ共感することの尊さを教えてくれた武雄さん
●私の腕の中で逝った和子さん
●私の中に生き続ける父
第2章 お金では買えない最期の贅沢……看取り士
●しあわせな死とは
●看取りの場面は奇跡の連続
●抱きしめて送るつもりが抱きしめられていた
●愛や喜び、すべてを受け渡す看取りの現場
●看取り士の立ち位置
●看取る人がしあわせになるための四つのポイント
①家族で肌の触れ合いを
②傾聴、反復、沈黙
③大丈夫と声をかける
④旅立つ人と呼吸を共有する
◆コラム:痛いと言われたらさする……ガン末期の方
●旅立つ人がしあわせになるための三つのポイント
①死を受容する
②お迎えは必ず来る
③旅立つ人は最期の状態を自分でプロデュースする
●看取り士の具体的な仕事
・余命宣告を受けてから始まる看取り士の仕事
・どこで死にたいのか、どのように死にたいのか
・重要な医師との連携
・身体を拭き、好きな服を着せてあげる
第3章 病院で死ぬしかない日本の制度
●病院で死ぬしかない現実
●家族が壁になる
・延命治療と家族のエゴという問題
・死んだらどうしようという不安
●延命治療をするとどうなるか
・胃ろうをしない選択、する選択
●私たちは子供たちに地獄を見せているのではないか!?
●病院で死ぬしかない制度に医療関係者も矛盾を感じている
●特別養護老人ホーム(特養)で実現すべき尊厳ある死
・「看取り加算」という制度ゆえに、自宅で死ぬことが難しくなっている─107
・施設に入り、最後は病院へ
・介護を受けている人の悲しみを受け止めたい
◆コラム:介護の現場
第4章 平穏に死ぬための準備をしよう
●60歳になったら必ず死の準備をする
・人は一人では死ねない
・家族で話し合う
●看取りとは、ひと昔前に行われていたことを取り戻すこと
●死は第二の誕生
◆コラム:魂と魂を重ねる時間
●死の恐怖を取り除く内観とは
●光を感じた瞬間
●母の死
◆コラム:死後も大切なこと……初七日・四十九日
●「1億総ヘルパー」時代に突入
●しあわせに旅立つための「エンゼルチーム」
●帰りましょう、帰りましょう……エンゼルチームの活動から
資料編 柴田さん頑張れ!!
……医師との対談と医師からの応援コメント
●医者が一番知らない平穏死
──長尾和宏医師に聞く
●融合医療を目指して
──日本心身医学会専門医 内科医師 岩田千佳
あとがき
※巻末資料:看取り士とエンゼルの仕組みをご利用いただくために